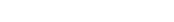共有地について思う
沖縄でも先祖代々受け継がれてきた不動産(土地)。一定の坪数を持つ不動産の継承について多くの課題が山積しているのではないでしょうか?
いろんな一定数の坪数のある土地はいろんな活用方法がありますね。アパート経営や駐車場経営などなど。
ただしこの一定数の土地が共有地でしたらどうでしょうか?
※これ1つの事例になります。
例えば100坪の土地に共有者3名(父親、父の兄弟2名)がいるとします。現在は3名の共有ですが、その3枚にそれぞれ3名の子供がいるとします。
将来的に3名×3名の9名の共有地になります。(自然の法則では)
3名の共有者であればこの100坪の土地を駐車場として賃貸した際に意思疎通はごく簡単なものだと思われます。意思疎通とは誰に貸す、アスファルトを敷く、賃料を上げる、固定資産税の納税などその土地の維持管理に必要な意思ですが、もし9名の共有地になったらどうでしょうか? その9名の意思疎通の整理は誰がする?もし9名の内本土に住む方がいた際に連絡が簡単につくのか?もし本土に行ったきり所在不明になった場合はどうなるのでしょうか?
連絡または取りまとめは誰がするのでしょうか?
多分誰も面倒な事はしたがらないのではないでしょうか?
また、これまでは共有地の処分に関しては賃貸やその管理に関しては全員の同意や過半数同意など煩雑なものがありました。(後述します)
土地の維持管理の意思疎通の取りまとめが一仕事になってきます。
不動産会社に委託する手もあります。しかし維持管理するためには共有者の同意が必要になってきます。
私は共有地ほど問題や課題を抱える不動産はないと思っています。
そのため今の共有者が少人数(ここでこ3名)のうちに何らかの対策を考えた方が良いと思います。
3名でも煩雑な物事が起こってくるでしょう。しかし3名以上になればさらに煩雑な物事が起こったり、トラブルの発生もありえます。
共有地は少人数のうちに解決策を考えてはいかがですか?
弊社ではそんな共有地をお持ちの方々と一緒に維持管理の方法を考えていきたいと思います。
共有地における処分(維持管理・売却)においては令和3年(施行:令和5年4月1日)に民法が改正されました。
※弁護士または司法書士にご相談ください。
民法262条の2
共有不動産の所在不明の共有者の持分を、他の共有者が取得できる制度を定めています。共有者が他の共有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合、裁判所は、共有者の請求により、所在不明共有者の持分を請求した共有者に取得させる旨の裁判をすることができます。
民法262条の3
共有者の他の共有者の所在を知ることができないときは裁判所に対し「譲渡(売却)」することを条件として譲渡する権限を付与することを請求できるとされています。