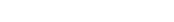家族信託組成例①
ご家族及び資産
①父親/84歳・・・・不動産(土地/評価額3000万円・建物評価額1000万円・預貯金1000万円)
②母親/80歳・・・・専業主婦
③長男/55歳・・・・会社員(配偶者、お子さん3名)
④妹/50歳・・・・専業主婦(配偶者、お子さん3名)
⑤弟/48歳・・・・・地方公務員(配偶者、お子さん無し)
まずは父親に家族信託の話をし、家族信託のプランニングを作成します。
※当該プランニング作成の内容が税務上の問題点が無いかを税理士と確認いたします。
⭕️内容は不動産(土地及び建物及び預貯金のうち1000万円を信託財産とします。
🔸委託者=父親
🔸受託者=ご長男
🔸受益者=父親
その後弟さんを除き(離島へ出稿中)ご家族一同集まって頂き家族信託のプランニングのお話をします。不在の弟さんにはzoomを使い遠隔にて当該プランニングをご説明いたします。
ご家族全員が当該プランニングを理解して頂きました。
契約書を作成し弁護士にリーガッチェックを行います。このリーガルチェックは当該家族信託契約書が信託法及び民法に沿った内容であるかをチェックしてもらいます。
その後弊社はまずその父親の預貯金を管理している銀行に行き「信託口口座」開設の可能性を確認いたします。➡️信託口口座派開設可能とのこと。
そして公証人役場において公証人による契約書の調印・公証を行います。(委託者・受託者も同席)
公証人の公証を経てその契約書を信託口口座開設銀行に持参して信託口口座開設を行い1000万円を信託財産といたします。
不動産(土地・建物)は司法書士によって「信託登記」を行ないます。
そしてこのご家族の「家族信託」がスタートいたします。
これが一連の流れとなりますが、そして受託者は信託財産の預貯金から定期的に受益者に生活費を拠出してあげるといった業務をはじめ委託者から託された財産を信託契約に基づいて適切に管理・運用します。具体的には、不動産(アパートなど)の管理や賃貸、預貯金の管理など信託目的に沿った活動を行います。また、信託財産に関する帳簿の作成や報告、受益者への定期的な報告も義務付けられています。
煩雑な業務は弊社に方で受託者をはじめ委託者をサポートして参ります。
(例:税務上不明な点を税理士と連携して円滑に税務を進めます)
このご家族は収益物件(アパート)をお持ちでなくご自宅及び土地そして現金を信託財産とします。利益は生じない信託になります。 ※信託財産である預貯金1000万円の利息は生じその利益となりますが。
ではなぜあえてこのご家族は家族信託を選んだのでしょうか?
それは父親が将来的に認知症になった時の1つの備えなのです。
家族信託をしないでいた場合、父親が認知症になればご自宅のある不動産は売却できません。
もし父親の介護に費用がかかった場合どうでしょうか? お子さんはそれぞれご家族をお持ちです。そのお子さんがまだ学生だったらどうでしょうか?学費を捻出しないといけないのにお父さんの介護費用も負担せざるを得ない場合だとお子さん家族の大きな負担となってきます。
その際に父親の介護費用及ぶ母親の老後の生活費の拠出に際して不動産を売却する手があります。
が残念ながらお父さんは不動産を売却できません。なぜなら認知症になっており意思無能力者となっており売却は無効となるのです。
しかし家族信託を設定していれば受託者であるご長男で売却できます。その売却益でお父さんの介護費用やお母さんの老後の資金として利用できます。
その後父親母親に相続が発生すれば残余財産はご兄弟で分割協議を行いそれぞれの安定した生活に活用できることになります。
これはあくまでも家族信託の一例です。いろんな家族の構成があります。そのご家族の構成を鑑みて弊社ではベストな家族信託のプランニングと支援を行って参ります。